株式会社キタムラ様
得られた定量データによって
検討段階の施策の効果にも自信。

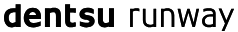
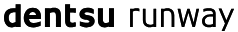
マーケティング活動では、生活者の意識や行動の変化を素早く捉えることが、これまで以上に重要になっています。特に広告効果の検証は、ブランド戦略やアロケーション戦略の意思決定にも影響するため、そのスピードと柔軟性が求められる場面が増えています。
こうした状況の中、株式会社電通ランウェイはセルフ型リサーチツール「Fastask」を導入し、社内で、調査の設計から配信、分析までを一貫して行える体制を整えました。これにより、従来は難しかったスピーディーな対応や、柔軟な設問設計を求めるクライアントの要望にも、迅速に応えられるようになっています。
本記事では、同社ソリューションセンター ソリューション開発部 部長の坂本 新様に、Fastask導入の背景や具体的な活用事例、そして少数精鋭チームが目指す今後の組織像についてお話を伺いました。
株式会社電通ランウェイ
/ ソリューションセンター ソリューション開発部 部長
/ 坂本 新様

――御社の事業について教えてください。
坂本様:
電通ランウェイは2019年に設立された比較的新しい会社で、現在は7期目を迎えています。電通グループの一員として、飲料・ヘルスケア・エンターテインメント・ECなど、外資系クライアントを中心にマーケティング全般の支援を行っています。
私どもの強みは、メディアコミュニケーションを軸に、クリエイティブやPRに至るまで一貫したサービスを提供できる点でしょう。特に重視しているのは、ブランド体験(ブランドエクスペリエンス)をどのように作るかという視点です。単にメディアに広告を出すだけでなく、生活者とどのように接点を持つかを設計し、クライアントの事業成長にしっかり貢献することが目標です。そのため、戦略のデザイン、コミュニケーションプランニングはもちろん、外部との協業も含めクリエイティブ制作、データ分析に至るまで、プロジェクト全体を先導できるマルチスキル人材を多く有することが最大の特徴です。
一人が広い領域を担当することで、いわゆる“伝言ゲーム”が起きにくく、意思の通ったアウトプットが可能になり、マルチスキルの利点が発揮されていると感じます。さらに、社員は電通グループのデータやツール、リソースといった豊富なアセットにアクセス可能です。そして、スピード感を持ってクライアントにサービスを提供し、クオリティも担保できることが、電通ランウェイの競争力の源泉だと考えています。
――坂本様の業務と会社との関わりについて教えてください。
坂本様:
私は現在、ソリューション開発部の部長を務めており、会社全体の「利益と価値」をどう生み出すかがミッションです。具体的には、電通ランウェイとして、クライアントに提供できる「選択肢」を増やすため、社内に不足している部分を先回りしてゼロから作り出し、提供する役割を担っています。
少し補足しますと、創業当初は専門分野に詳しい人材が不足していました。たとえば、電通には顧客データ活用の基盤であるPeople DMP※1や、デジタル広告の分析基盤となるSTADIA※2があり、これらはデータに特化したソリューションです。私たちの部署では、それぞれの案件に応じて活用方法をサポートすることもあり、調査が必要な場合には、ソリューション開発部の持つリソースやノウハウを社内の各部門へ展開し、相互に補完し合える体制づくりを進めています。最近では会社として教育や採用にも注力しており、ソリューション開発部は社内の採用領域への支援も行っています。
2030年までの中期経営計画では、ソリューション開発部がコンサルティング領域にまで踏み込むことを目標として掲げています。その実現に向けて、まずは電通ランウェイ自身をクライアントと見立て、自社が抱える課題と正面から向き合う姿勢を大切にしたいと考えています。専門領域や社内の相談対応においては、「徹底的なハンズオン型(積極的関与)」の姿勢でメンバーを支援していくつもりです。
また私は2021年に電通ランウェイへ入社しました。それ以前は商社や調査会社で、データ基盤やデータ分析を中心にキャリアを積んできたため、電通ランウェイではTVや広告などのデータに関する説明も比較的スムーズに行えました。今後は、自分の強みである「データ分析」と「ロジカルな課題設定および解決力」をさらに広めていきたいと考えています。
※1 People Driven DMP®: 電通グループが提供する、顧客データを活用するためのデータマネジメントプラットフォーム(DMP)のこと。様々なオーディエンスデータ、メディア接触データ、購買データなどを統合し、より効果的なマーケティング施策を実現する基盤。
※2 STADIA:テレビ視聴データとデジタル広告を連携させた統合マーケティングプラットフォームのこと。テレビCMの効果検証や、コネクテッドTVへのターゲティング広告配信、オンラインとオフラインを統合した分析などに活用。
――Fastaskの導入をご検討いただいた理由やきっかけについて教えてください。
坂本様:
Fastaskを選んだ最大の理由は、検証結果が速く得られることです。「できないをなくす武器」としてFastaskを導入することで、従来の課題を解決できました。また、電通グループ内には調査リソースが整っていますが、部門間の制約もあり、必ずしも誰でも平等に使えるわけではありません。その中で、私たちのような部門がFastaskを活用し、独自にスピーディーに動ける環境を整えることは、業務の柔軟性やクライアント対応力を高めるうえでも非常に重要だと考えています。
検討のきっかけは、電通ランウェイは電通本社と協業することも多く、その仕事を通じてFastaskを紹介されたことです。セルフ型リサーチツールとして、コストとスピードの両面で魅力を感じました。外資系企業を中心に、クライアントからは根拠となる数値を厳密に求めれられることがよくあり、「エビデンスが欲しい」という要望が頻繁に寄せられます。しかし、従来のように調査会社へ依頼すると、要件の整理やスケジュール調整に時間がかかり、調査結果が返ってくるまで7営業日以上かかることも珍しくありません。そのタイムラグが、広告施策の検証に間に合わないという課題につながっていました。できないことはできないと伝えるにしても、どうすればできるようになるかを考え続ける必要があり、その意味でもFastaskは解決の糸口になったと感じています。
この10年で、広告の「結果」に対する考え方は大きく変わりました。以前はリーチが取れれば十分とされていましたが、今は「その広告がどれだけ好感度に影響したか」「どのようなブランドリフトがあったか」まで測ることが求められています。しかも、それを施策直後に報告できるスピード感が必要です。私自身リサーチの実務経験があるため、設計から集計、分析まで一貫して行えるFastaskの操作性や自由度には大変助けられています。
一般的にデジタル広告ではコンバージョンで効果を測れますが、インフルエンサーのインプレッションやクリック数が増えても、「どんな気持ちでクリックしたのか」は分かりません。クリックの背景を知るためにもFastaskは非常に有効です。従来の方法で大量のABテストを行うこともできますが、広告クリエイティブを大量に作るのは現実的に難しい面もあります。Fastaskを使えば、なぜクリックしたのか、その理由まで知ることができ、消費者のブランド体験に直結する結果が得られます。
――Fastaskの活用方法について教えてください。
坂本様:
基本的に、広告キャンペーンを実施した際は、すべてのファネル(認知、興味、来店・購買)を計測し、次のマーケティング施策に活かす流れを確立しています。Fastaskによってブランドリフト調査も可能になり、消費者が広告に接触したり実店舗に来店したことで、購買意欲がどの程度高まったかを把握できるようになりました。これにより、広告の仮説に対して確かな検証データが得られるようになっています。
また、 Fastaskのスピード感は、急ぎの案件に最適です。調査後7営業日以内に結果が得られるのは、従来のリサーチツールにはなかった特徴です。そして、自分で自由に設計できる点もFastaskの大きな魅力だと感じています。
最近ではクライアントから「その行動に至った背景は何か?」といった感情や思考の深掘りを求められることも増えています。そのような場合は、リサーチ結果を集計ツール「Fxross」から都度取得しています。また、自分で作成した設問設計が正しいかどうかを確認してもらえるリサーチャーの存在もありがたいです。ただし、調査自体は矛盾を抱えながら設計する場面もあるため、リサーチャーの柔軟性がもう少し高まると良いと感じることもあります。今後はその点も改善されると聞いており、期待しています。

――Fastask導入後の効果について教えてください。
坂本様:
まず大きな効果として、突発的な案件や変更の多いプロジェクトにも対応できる心理的な安心感が高まりました。これまで社内のチームは、クライアントに「調査は難しいかもしれません」と答えることもありましたが、今では、「できますよ。」と返せるようになったのは大きな変化です。調査を実施するかどうかはクライアントの判断ですが、私たちとしてはしっかりと要望に応えられるようになったことが、最大の導入効果だと考えています。
さらに、Fastaskの導入によって調査が短期間で完結することに皆が驚き、従来は対応できなかった突発的な案件でも調査データを入手できるようになりました。その結果、調査のハードルが下がり、「まずは調べてみよう」という意識が部署内に広がっています。また、社員自身がピンポイントやカスタムメイドの調査もできるようになったことも、大きな成果だと感じています。
――満足度を教えてください。また、どのような会社におすすめでしょうか?
坂本様:
Fastaskに対する満足度は「5点満点中4」といったところです。ツールとしての性能や使いやすさは高く評価していますが、最大限に活用するには、利用者側の準備や工夫、特に調査設計のスキルが必要です。
たとえば、調査設計支援などのサポートもありますが、前提として自分で与件をきちんと整理し、設計担当者に丁寧に伝える必要があります。しかし、その際に御社に依頼すると、スピード感が損なわれる可能性もあります。「満足度5点」を目指すには、利用者とサービス提供側が歩み寄りながら最適解を見つけていくことが大切です。そのためには、我々ユーザー側もリテラシーを高める必要があると感じました。
導入をおすすめしたいのは、小規模から中規模の企業です。大手企業はすでに外部調査会社と連携しているケースも多いでしょうが、中規模企業であればスピード感のあるリサーチが必要な場面も多いと思いますので、向いていると思います。
また、Fastaskは営業部門以外でも活用できるツールであることを広く知っていただきたいと考えています。もちろん、私たちのようなソリューション部門やマーケティング部門でも十分に活用可能です。最近では、弊社の認知調査に使用しました。そこから発展し、人事・採用部門でも有効に使えるのではないかと考えるようになっています。たとえば、採用広報の反応を確認したり、自社ブランドに対する認知度やイメージを把握したりする用途にも適しています。コストを抑えながら現状を見極めたい企業にとって、非常に有用なツールだといえるでしょう。
――今後の展望について教えてください。
坂本様:
先ほどもお伝えした通り、現在弊社では「Expansion2030」という中期経営計画に取り組んでいます。具体的には、売上で約3.7倍、利益で約2.9倍の成長を目指しており、非常にチャレンジングな目標です。
これまで外資系クライアントを中心に支援してきましたが、今後はグローバル展開を目指す日本企業の支援にも力を入れていきたいと考えています。その中で、電通グループのリソースを活かしつつ、電通ランウェイとしての独自性をしっかり確立することが重要です。そのためには、組織としての基盤強化が不可欠であり、社員一人ひとりのスキル、特にマルチスキル人材の重要性がさらに高まると考えています。
また、生成AIの活用も大きなテーマです。ただし、AIを活用するうえで最も大切なのは「問いを作る力」や「依頼内容を正確に言語化する力」です。これはFastaskの設問設計でも同じで、何をどう聞くかを考える過程が、社員の思考力を鍛える場にもなると思います。今後も、Fastaskを活用しながら、仮説検証による消費者のブランド体験をより精緻なものにしていくつもりです。
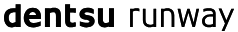
| 社名 | 株式会社電通ランウェイ様 |
|---|---|
| 事業内容 | 2019年に株式会社電通のメディア推進部門からスピンアウトして設立された総合広告会社。広告コミュニケーションを中心に、デジタルテクノロジーの進化や生活者の行動多様化に合わせた統合ソリューションを提供。電通グループのリソースを活用しながら、少数精鋭で、変化の激しい市場に対応できる柔軟性とスピード感を持ち、サービスを提供している。 |
| 設立 | 2019年4月1日 |
| 従業員数 | 約170名(2025年7月現在) |
※ ページ上の内容は公開時点の情報です。